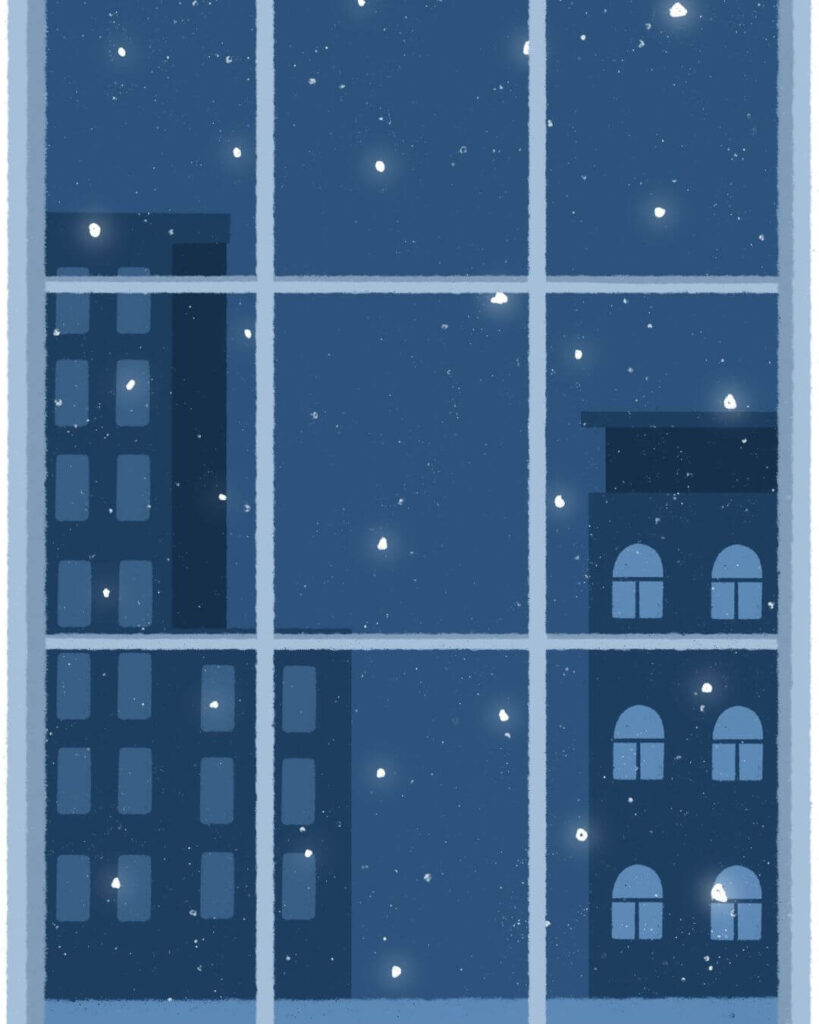-

NO.074
新宅祭とは?新築の節目を彩る日本の伝統儀式

新しい住まいが完成したとき、家族の安全と繁栄を願って行われる「新宅祭(しんたくさい)」。これは、地鎮祭や上棟祭と並ぶ、日本の住宅建築における重要な神事のひとつです。新宅祭は、家が無事に完成したことへの感謝と、これからの生活の安寧を祈る儀式であり、神棚を設けて神様をお迎えすることで、家に神霊が宿るとされています。
新宅祭は、神職を招いて神棚の前に祭壇を設け、米・塩・水・酒・野菜・果物・海産物などを供えます。
儀式は「修祓(しゅばつ)」から始まり、「降神」「献饌」「祝詞奏上」「清祓」「玉串奉奠」「撤饌」「昇神」などの順で進行します。
特に水回りや玄関など、災いが入りやすいとされる場所を重点的に清めるのが特徴です。
また、神棚がある場合はその場でお祓いを行い、神様をお迎えして家内安全を祈願します。
神棚がない場合でも、家全体を清めることで神様の加護を願うことができます。
地鎮祭は、建築前に土地の神様に工事の安全を祈願する儀式です。
これに対して新宅祭は、建物が完成した後に行われる感謝と祈願の儀式です。
地鎮祭では土地の使用許可を得る意味合いが強く、祭壇は屋外に設けられます。
一方、新宅祭は室内で行われ、家そのものに神霊を宿すことを目的としています。
近年では、マンションや中古住宅の購入時にも新宅祭を行う家庭が増えています。
神社によっては出張祭典を受け付けており、神職が自宅に訪れて儀式を執り行ってくれます。
初穂料やお供え物の準備などは事前に相談することで、スムーズに進めることができます。
新宅祭は、家族が新しい生活を始めるにあたって、心を整え、感謝と祈りを捧げる大切な時間です。
日本の伝統文化として、これからも受け継がれていくことでしょう。
CASA MAGAZINE
幸せで楽しい日常を求める人のための
暮らしと家づくりマガジン
同じカテゴリの記事
OTHERS
その他の記事を見る